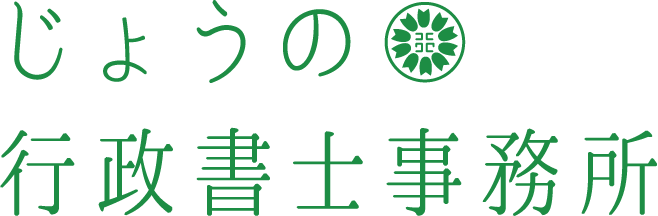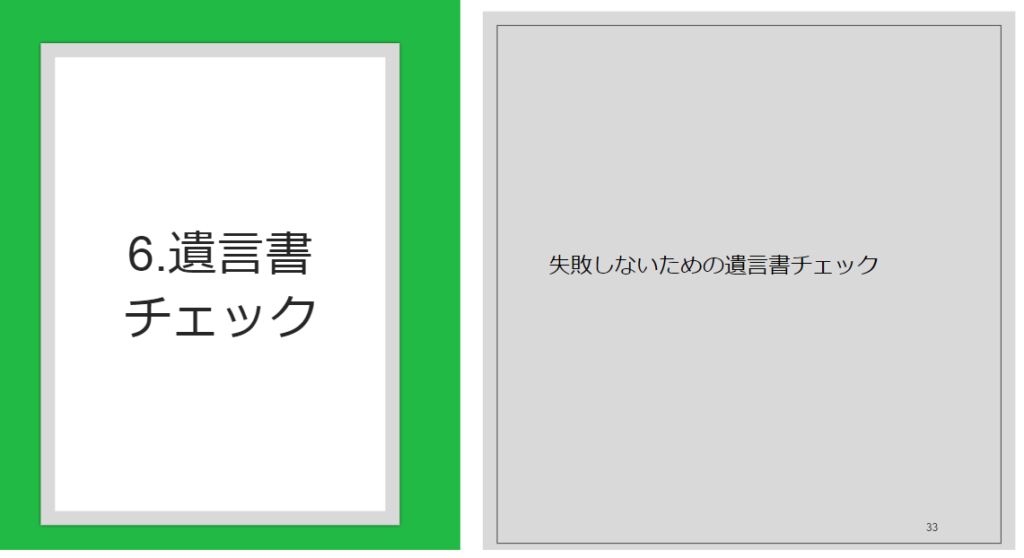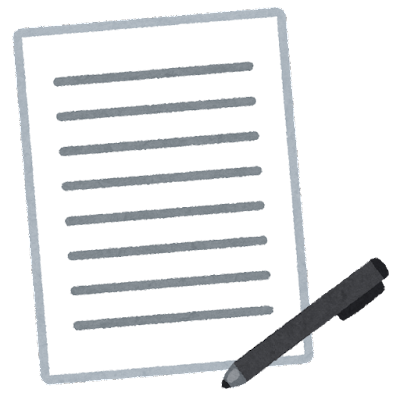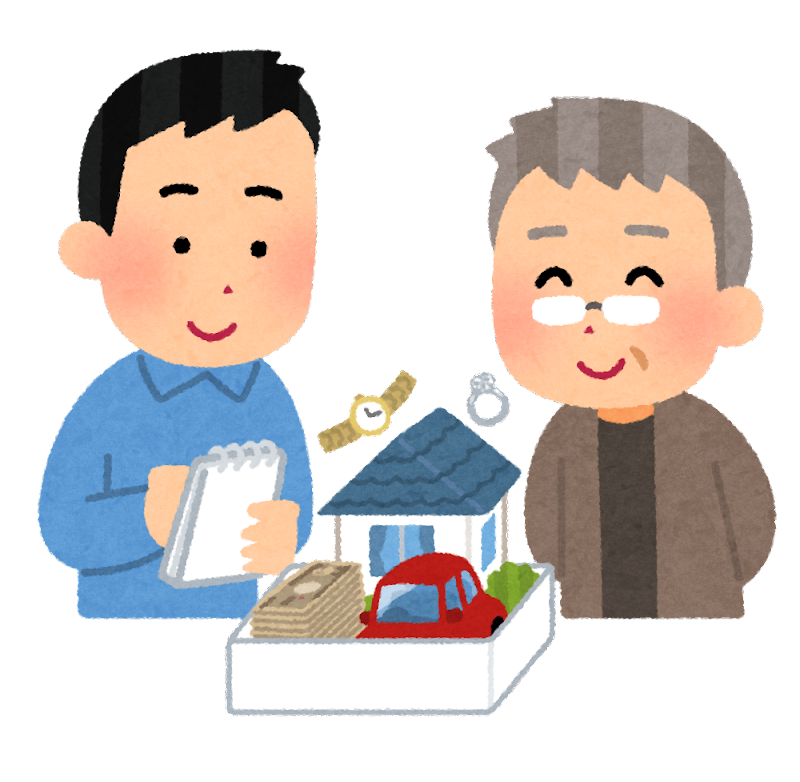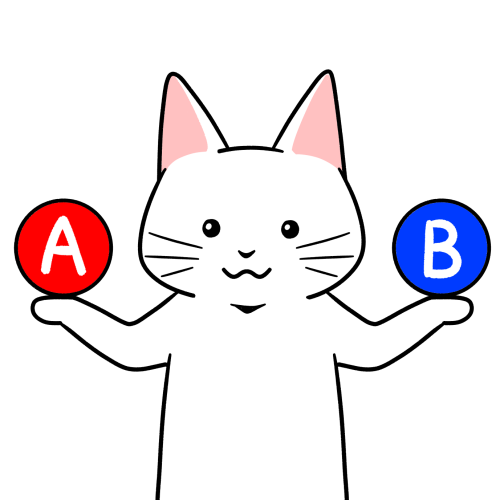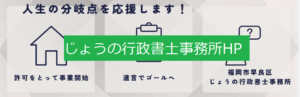社会福祉法人の運営に携わる皆様、こんにちは!行政書士の城野です。
社会福祉法人は、その高い公共性から、一般の会社以上に透明で公正な運営が求められます。
「うちの法人は大丈夫」と思っていても、意外と見落としがちなのが**「利益相反取引」**のルールです。
特に、**「理事個人が経営する会社と法人が取引している」**といったケースは、気づかぬうちに法律違反となっている可能性があり、注意が必要です。
今回は、社会福祉法人の理事や評議員の皆様が知っておくべき「利益相反取引」の基本ルールを、分かりやすく解説します!
## そもそも「利益相反取引」って何? 🤔
利益相反取引とは、簡単に言えば、「法人の利益」と「理事個人の利益」がぶつかってしまう(相反する)可能性のある取引のことです。
例えば、理事が法人に対して不当に高い価格で物品を売りつけたり、逆に法人の財産を不当に安く買い取ったり…といった事態を防ぐためのルールですね。
法律では、主に2つのパターンが定められています。
- 直接取引:理事個人が、自分自身のために法人と契約を結ぶケース。(例:法人が理事個人の土地を買う)
- 間接取引:法人と理事以外の人との取引だが、実質的に理事の利益になるケース。
## 【最重要ポイント】理事の「会社」との取引は利益相反です!
「理事個人との取引ではないから大丈夫」と思っていませんか?実は、それが大きな落とし穴です。
結論から言うと、理事が実質的に支配している会社と社会福祉法人が取引する場合も、利益相反取引に該当します。 このような取引には、法人の利益が不当に害されることのないよう、特別な手続きが法律で定められています。
<「実質的に支配」とは?>
- 理事本人が、相手企業の株式の過半数を保有している
- 理事本人が、相手企業の代表取締役である
- 理事とその親族で、相手企業の役員の過半数を占めている
上記のようなケースが典型例です。
## もし利益相反取引を行う場合は?守るべき3つのステップ
利益相反取引がすべて禁止されているわけではありません。法人にとって必要な取引である場合もあります。
その場合は、必ず以下の適正な手続きを踏む必要があります。
ステップ①:理事会で事実を説明し、承認を得る
まず、取引を行う理事は、その取引の内容、金額、必要性といった重要な事実をすべて理事会で開示し、承認を得なければなりません。
これは、取引の妥当性を理事会全体でチェックするための重要なプロセスです。
ステップ②:当事者の理事は「議決」に参加しない
承認を決議する際、その取引の当事者である理事は、議決に加わることはできません。
自分の取引に関する議決に自分自身が参加できてしまうと、公正な判断が期待できないからです。
ステップ③:取引が終わったら、遅滞なく理事会に報告する
承認された取引を実行した後も、その理事は「取引が無事終わりました」という結果を、遅滞なく理事会に報告する義務があります。
## もし手続きを怠ったら…?考えられる2大リスク 😨
「面倒だから」「これくらいなら大丈夫だろう」と手続きを省略してしまうと、法人や理事個人に重大なリスクが生じます。
リスク①:理事個人への損害賠償請求
もし、手続きを経ない利益相反取引によって法人に損害が生じた場合、その取引に関わった理事は、法人に対して損害を賠償する責任を負うことになります。これは理事個人の財産で支払う必要があります。
リスク②:社会的信用の失墜
社会福祉法人にとって、地域社会や行政からの「信頼」は何よりの財産です。不適切な取引が明らかになれば、監査での指摘や行政指導の対象となるだけでなく、「あの法人は運営が不透明だ」という評判が立ち、寄付の減少や事業運営そのものに悪影響を及ぼす可能性があります。
## まとめ:健全な法人運営のために
いかがでしたでしょうか。利益相反取引のルールは、理事の活動を縛るためのものではなく、法人そのものを守り、その高い公共性と信頼性を維持するための大切な仕組みです。
最後に、簡単なチェックリストをご用意しました。
【利益相反取引 チェックリスト】
- □ 法人と取引する相手は、理事やその親族が経営する会社ではないか?
- □ もし該当する場合、その取引は理事会にきちんと報告されているか?
- □ 理事会の議事録に、承認決議の記録が残っているか?
- □ その決議の際、当事者である理事は議決に参加していないか?
一つでも「?」がつく項目があれば、一度立ち止まって確認してみてください。
法人のガバナンス(組織統治)は、日々の地道な確認作業の積み重ねによって成り立っています。この記事が、皆様の法人の健全な運営の一助となれば幸いです。
ご自身の法人の取引についてご不安な点や、ガバナンス体制の整備についてのご相談がございましたら、お近くの行政書士などの専門家にお気軽にお尋ねください。