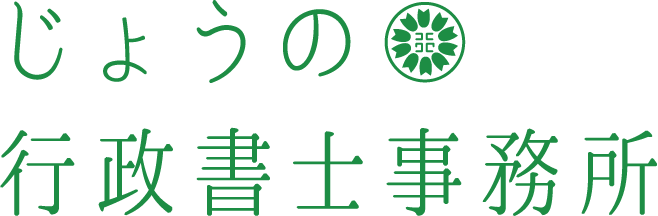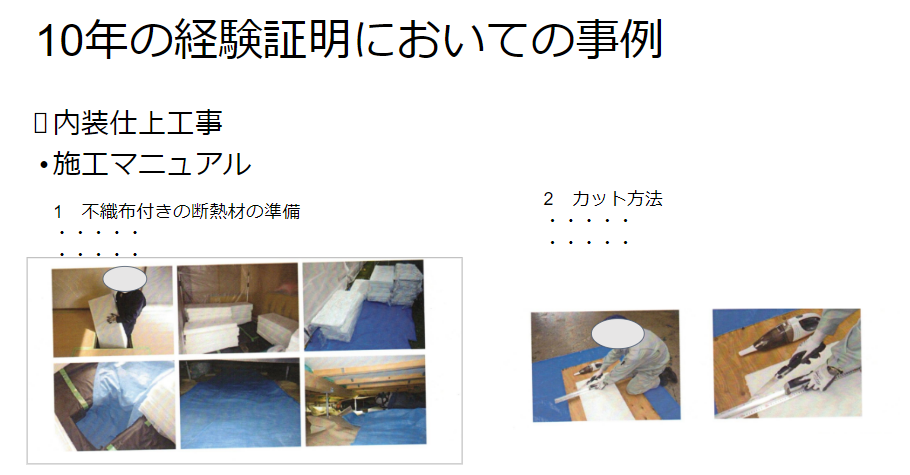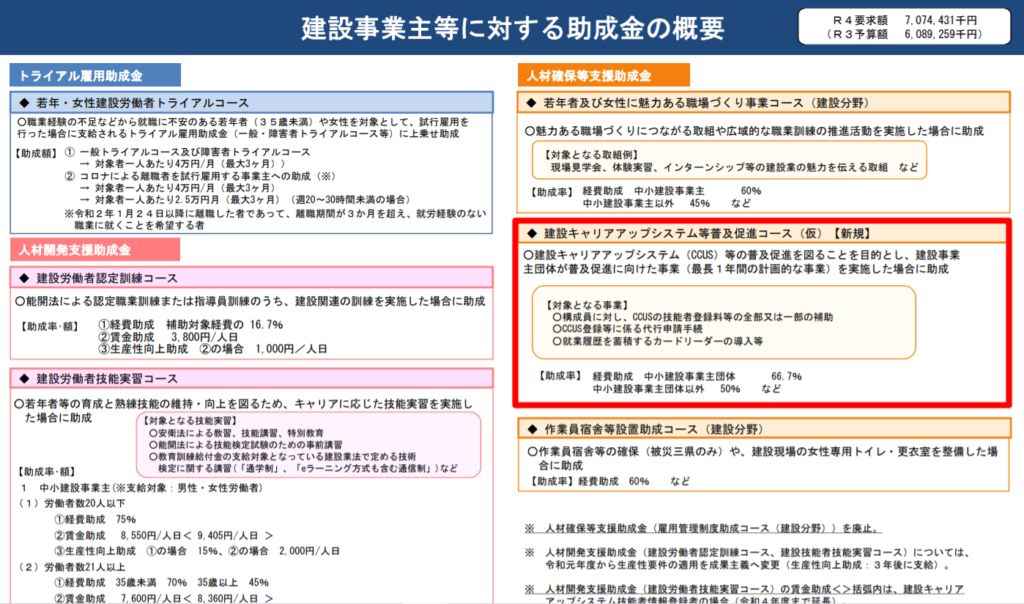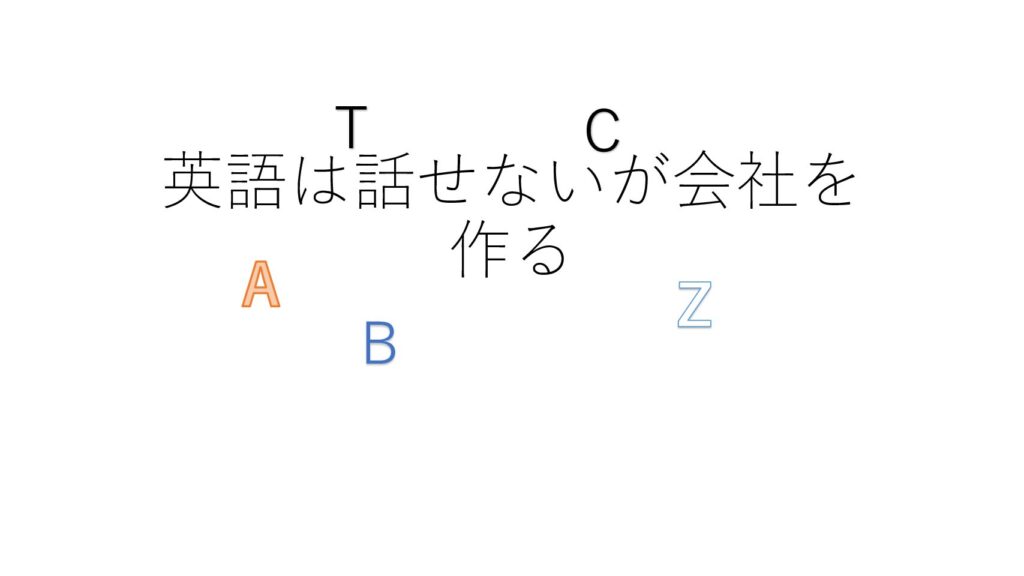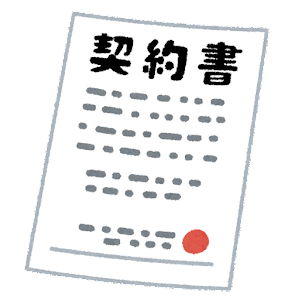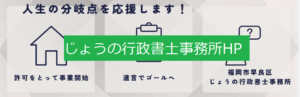こんにちは!企業の法務・コンプライアンスをサポートする行政書士です。
突然ですが、あなたの会社では「車両管理規定」を整備していますか?
「社用車はあるけど、特に細かいルールは決めていない」「マイカーを業務で使うことがあるけど、口頭での許可だけ」…そんな企業様も少なくないかもしれません。
しかし、その状態は非常に危険です。万が一、従業員が社用車で事故を起こしてしまった場合、会社は多額の損害賠償責任を負う可能性があります。従業員の尊い命、そして会社の未来を守るためにも、車両管理規定の整備は待ったなしの経営課題と言えるでしょう。
この記事では、日々多くの中小企業の皆様からご相談をいただく行政書士の視点から、なぜ車両管理規定が必要なのか、そして具体的にどのように作ればよいのかを、分かりやすく解説していきます。
◆ そもそも「車両管理規定」とは?
車両管理規定とは、その名の通り、会社が所有または使用する車両(社用車)の管理・運用に関するルールを定めた社内規程のことです。いわば、**「会社のクルマに関する公式ルールブック」**です。
この規定の対象となるのは、一般的に以下の通りです。
- 対象者:役員、正社員、契約社員、パート・アルバイスなど、会社の業務で車両を運転する可能性のあるすべての人
- 対象車両:会社が所有する車両(社有車)、リース契約している車両、従業員が所有する自家用車(マイカー)を業務で使用する場合
このルールブックを整備することで、会社は車両を安全かつ効率的に管理し、様々なリスクから身を守ることができるのです。
◆ なぜ必要?車両管理規定を整備すべき3つの理由
「就業規則があれば十分では?」と思われるかもしれません。しかし、車両の利用には特有のリスクが伴うため、専門の規程を設けることが不可欠です。その主な理由を3つご紹介します。
理由1:事故発生時の法的リスクを軽減するため
従業員が業務中に交通事故を起こした場合、会社は民法上の「使用者責任」や、自動車損害賠償保障法上の「運行供用者責任」を問われる可能性があります。これは、会社が被害者に対して、運転者である従業員と連帯して損害賠償責任を負うという、非常に重い責任です。
車両管理規定を整備し、運転者の資格を定め、安全運転教育の実施や車両の点検を義務付けるなど、会社として安全配るべき義務を尽くしていたことを明確に示すことができれば、万が一の際に会社の責任が軽減される可能性が高まります。これは、会社を守るための重要な「盾」となるのです。
理由2:車両の適正な管理とコストを最適化するため
車両管理規定は、リスク管理だけでなく、経営の効率化にも繋がります。車両に関するあらゆる「モノ」と「カネ」の流れをルール化することで、どんぶり勘定を防ぎ、コスト管理を徹底することができます。
理由3:従業員の安全意識を高め、コンプライアンスを徹底するため
明確なルールがない状態では、従業員一人ひとりの安全意識にばらつきが出てしまいます。車両管理規定によって、飲酒運転や「ながらスマホ」の絶対禁止などを具体的に定めることで、全従業員が共通の規範を持つことができます。これは、従業員に対して「会社は安全を何よりも重視している」という強いメッセージを発信することに繋がります。
◆ 法的義務!「安全運転管理者」の選任を忘れていませんか?
車両管理規定の話を進める上で、絶対に避けて通れない法律上の義務があります。それが、道路交通法第74条の3に定められた「安全運転管理者」の選任義務です。
一定台数以上の自動車を使用する事業所は、法律に基づき「安全運転管理者」を選任し、公安委員会に届け出なければなりません。
【選任が必要な事業所の基準】
- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している
- その他の自動車を5台以上使用している
(※大型自動二輪車または普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算します)
この基準に該当する場合、安全運転管理者の選任は企業の義務です。選任義務があるにもかかわらず選任していなかったり、届出を怠ったりした場合には罰則も定められています。
安全運転管理者は、運転者の状況把握、運行計画の作成、安全運転指導、運転日誌の管理など、事業所の安全運転を確保するための業務を統括する重要な役割を担います。そして、車両管理規定は、この安全運転管理者が業務を遂行するための具体的な根拠・手段となるのです。
◆【作り方】車両管理規定に盛り込むべき10の重要項目
では、実際に車両管理規定を作成する際に、どのような項目を盛り込むべきでしょうか。ここでは、必ず押さえておきたい10の項目をご紹介します。
- 総則(目的)
この規定が「業務の円滑な遂行、車両の安全な運行、交通事故の防止」などを目的とすることを明確に宣言します。
- 適用範囲
誰(全従業員、運転業務従事者など)に、どの車両(社有車、リース車、業務利用するマイカー)に適用されるのかを具体的に定めます。
- 管理体制(安全運転管理者等)
車両管理の最高責任者を定めるとともに、道路交通法に基づき選任された安全運転管理者を明記します。安全運転管理者が各車両の管理や運転者への指導・監督を行う旨を定め、責任の所在を明らかにします。
- 運転者の資格
社用車の運転を許可する条件を定めます。(例:勤続1年以上、運転経験3年以上、過去1年間に免許停止処分がないこと、など)
- 車両の使用ルール
業務目的外での使用(私的利用)の可否、使用する際の手続き(使用許可申請書の提出、承認フロー)、車両の鍵の管理方法などを具体的に定めます。
- 運転者の遵守事項
安全運転義務、法令遵守はもちろん、出発前の日常点検、運転日報の作成・提出、長距離運転時や悪天候時の注意点、飲酒・過労運転の禁止などを具体的に規定します。
- 車両の維持管理
日常点検、定期点検、車検の実施責任や、車両を常に清潔に保つことなどを定めます。
- 交通事故・違反発生時の対応
事故や交通違反が発生した際の報告義務(誰に、何を、いつまでに)、警察や保険会社への連絡手順、現場での対応方法などを時系列で分かりやすく定めておきます。
- 損害賠償
運転者の故意または重大な過失によって会社に損害が生じた場合、会社がその従業員に対して損害の一部を求償することがある旨を定めます。
- マイカーの業務利用
マイカーの業務利用を許可する場合のルールです。許可基準(任意保険の加入状況確認は必須)、使用申請手続き、ガソリン代などの費用弁償の計算方法などを定めます。
◆ 作成・運用時の3つの注意点
規定は作って終わりではありません。実効性のあるものにするために、以下の3点に注意してください。
- 実態に合わせる
インターネット上の雛形をそのまま使うのではなく、自社の業種、規模、車両の使用頻度などの実態に合わせてカスタマイズすることが重要です。
- 周知徹底する
作成した規定は、社内説明会や研修を実施して、全従業員に内容を正しく理解してもらう必要があります。入社時の研修に盛り込むのも効果的です。
- 定期的に見直す
道路交通法などの関連法令が改正されたり、会社の状況が変化したりした場合に備え、少なくとも年に一度は内容を見直しましょう。
◆ まとめ
車両管理規定は、単なる形式的な書類ではありません。それは、**交通事故という最悪の事態から、会社と従業員、そしてその家族の未来を守るための「命綱」**です。
そして、一定規模以上の事業者にとっては、安全運転管理者の選任と、その活動の基盤となる車両管理規定の整備は、法律が要請する社会的責務でもあります。
「自社に合った規定の作り方がわからない」「安全運転管理者の選任手続きについて知りたい」など、ご不明な点がございましたら、ぜひ一度、私のような専門家にご相談ください。リスクを未然に防ぎ、安心して事業に集中できる環境づくりを、全力でサポートさせていただきます。